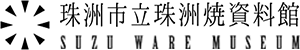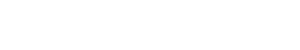本文

焼き物の生産は、(1)製作工程-1.成形2.調整3.加飾と、(2)焼成工程に大別される。次に、瓷器系中世陶器と対比しつつ、その特質を要約しよう。
製作工程のうち、「成形」は粘土紐巻き上げにより概形をこしらえる一次成形と、叩き締め(甕・中壺類)、あるいはロクロ挽き(小壺・片口鉢類)によって器形を整える二次成形がある。叩き締めは須恵器系独自の技法であるが、中壺の底部鉢形を片口鉢と同じ「紐ロクロ成形」、継ぎ足した胴部を「紐叩打成形」とする二段合成技法は、珠洲陶器固有のものである。
叩打は、上からみて右回りのロクロ回転を利用し、内面にこぶし大の円礫または陶製扁円形の押圧具を当て、普通木目と平行に条溝を刻んだ打圧具で、外面を縦に連続して叩き締める。右下がり一方向のほかに、上→下、下→上を交互に繰り返し叩き目を交差させ綾杉状とした個体も多い。珠洲1・2期には装飾叩打文の原体の使用例があるが、山形県楯ノ腰経塚例では、24列にわたり約150回前後の叩打痕が確認できる。なお、5期以降定量生産される研磨壺は、通有の紐叩打成形後、ヘラ状器具で丁寧に叩き目を削るもので、珠洲陶器独特の技法である。
小物は大体紐ロクロ成形品であるが、中壺底部の鉢形や口頸部の成形に、器面を入念、平滑に仕上げる調整工程を考慮すると、ロクロへの依存度が瓷器系より相対的に高かったとみられる。器高30cm台の製品は、初期の中壺の一部の砂底を除くと、例外なく糸切り底で、1期に限って右回り回転糸切り痕が認められる。
以上のほか、仏神像でみられる「型作り技法」、五輪塔や分銅型製品など小型品の仕上げに「切削技法」、甕壺類の底部円盤、装飾壺・瓶類の把手・注口部等の部材や付属品のほか、陶錘・陶製押圧具などは「手捻り技法」によって製作されており、水瓶の口頸部等の二次成形には「絞り技法」が時折りみられる。


「調整」は、成形に伴うロクロナデを除く二次調整であるが、製作工程が全体に省力化され、製品が粗造化した中世陶器では、体系的な技法は見出しにくい。片口鉢や一部壺類の底側面にみる「削り技法」、瓶類で器面の質感を出すための「磨き技法」、甕壺類内面の押圧痕の消去や外底面の部分的な軽い調整のための「撫で付け・撫で回し技法」などが一般的に認められる。
「加飾」は製作最後の工程であって、(A)ロクロの回転運動を利用したものと、(B)器体を静止した状態で施文したものに分かれる。前者は、壺・片口鉢、稀に甕を対象にした変化に富む「クシ目文」に代表され、ロクロ成形への依存度の高い珠洲陶器の製作技術と緊密に結びついて発達を遂げた。後者には、(a)描出技法(刻文・刻画・刻銘)と(b)押捺技法(刻印)があり、ほかに叩打技法に装飾文原体を用いる場合がある。
[鉢の文様]

次に焼成工程は、須恵器窯を肥大した無階単房の半地上式窖窯での「還元炎くすべ焼成」として約言でき、甕壺類の「紐叩打成形」とともに、須恵器系中世陶器の指標となることはいうまでもない。珠洲窯の窯構造については、わずかに発掘調査された珠洲市法住寺3号窯と計測調査の行われた西方寺1号窯のデータがあるにすぎない。室町前期に帰属する前窯は、焚口部と焼成部上半から煙道部分が損壊していたが、長舌状を呈し、全長9m以上、床最大幅3.6m、勾配23~26度を測る幅広の長舌状を呈し、4枚の床面が確認された。焚口には簡略な覆屋をかけ、前面に径7mばかりの前庭部が造成されていた。珠洲窯終末期の西方寺窯は、法住寺窯の南西1.6kmにあって、燃焼部と煙道部を亡失するが、焼成室の大半は天井が完存する。現存長約13m、床面幅3.2~1.2m、高さ1~1.1m、勾配約28度を測る。立面低平なカマボコ形を呈する地下式窖窯である。この他、東北の珠洲系窯として、秋田県大畑窯(2期)は全長14.4m、勾配20度程度の長舌状をなす半地上式窖窯であった。

このように、瓷器系通有の分炎柱を具備せず、終末期を除けば半地下式に構築されているものの、須恵器の数倍の大形窖窯である点は瓷器系諸窯と同じで、西日本の須恵器系諸窯と異なる。
ところで、窯構造と焼成技術は、北陸でも越前・加賀両窯が瓷器系として定着したのに対し、珠洲窯がなぜ須恵器系の生産技術を選択したのかという基本的な課題とかかわっている。この点については、かつて瓷器系と須恵器系の差異を、使用陶土に規定された燃焼効率差と理解し中世末期の北東日本海域における珠洲窯と越前窯の競合から、越前窯の一円市場化として帰結した理由を、この原理によって説明しようとした。しかし、その後胎土の理科学的分析の結果は、各地の古代須恵器窯と中世窯では、近似した陶土を使用する場合の多いことが指摘され、また、須恵器や中世陶器の焼成実験の結果も、赤褐色と暗灰色の器肌の発色の違いは、火止め後の冷却段階における窯の密閉作業の可否によってもたらされたとして、瓷器系窯・陶器の優越性を過大評価できないことが明らかになりつつある。
珠洲陶器の陶土分析未了の現状での論断はひかえねばならないが、分炎柱の有無に端的に具現される瓷器・須恵器両系列の窯構造は、生産技術系譜の差異であって、窯構造自体が酸化炎・還元炎両燃焼を決定するものではないと考えれば、珠洲窯が須恵器の生産技術を選択したのは、陶土という自然的要因よりも、生産技術系列の継承という人文的要因の規定性が大きかったからであろう。ただ、そうすれば、製品や大形の窯体にみられる東海の瓷器系の影響をどう評価するかが、改めて問われることになろう。