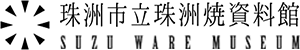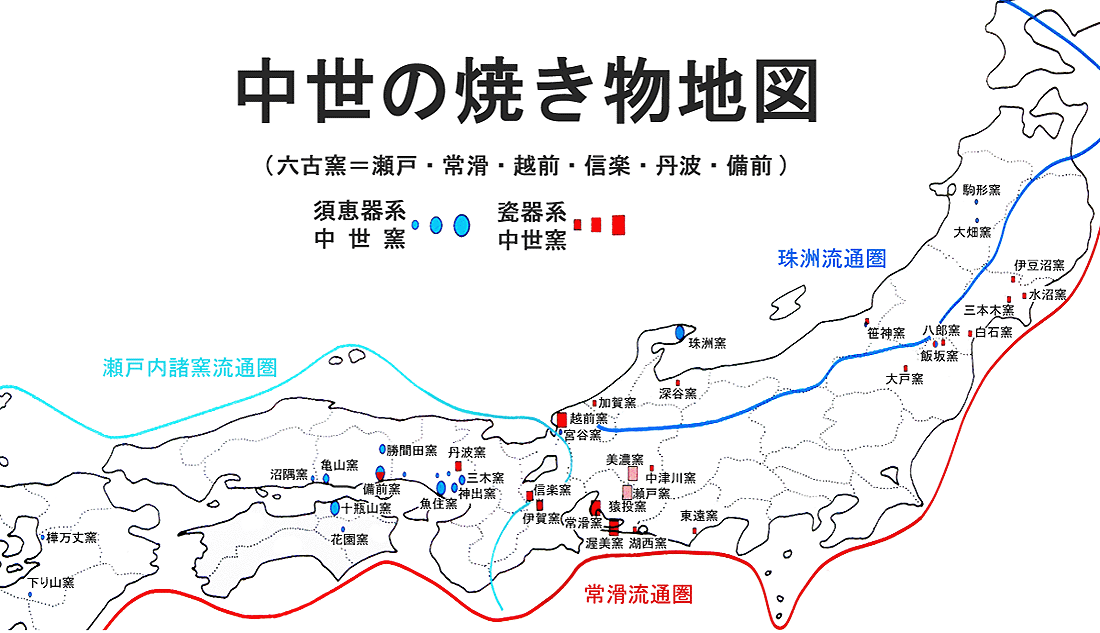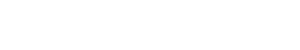本文
中世の焼き物には、各地で生産された土製(土師器・瓦器)、陶製の食膳具(碗・皿)と土製の煮炊具(釜・鍋)、広域に流通した陶製の貯蔵・調理具(甕・壺・すり鉢)がある。これら国産の日常容用器は、食膳具(碗・皿・鉢)を主体とし、高価な四耳壺・瓶子・水注・合子などを含む中国陶磁と併用された。瀬戸・東濃陶器は、中国陶磁をモデルにした国内で唯一の高級施釉陶器であり、宗教具や茶陶など奢侈品が、東日本を中心に広域に流通した。
もちろん、焼き物以外に、漆器・木器や曲物も食膳・宗教具を構成する重要な文物であった。また、鉄器が煮炊具(鍋)にはたした役割りも軽視できず、やや特殊なものとして、九州産の滑石製石鍋も列島規模で流通している。このほか、特権階級の食膳・宗教具(碗・皿・水瓶等)には金・銀・金銅・青銅製品も使用された。
これら各種の土器・陶器の器質や器種は、個々には古代以来の伝統を負い、地域性を濃厚にとどめているが、組成のあり方は、中世の商品的流通経済の発達に相即して大きく変容している。たとえば、飯を盛る食器は、地域によって須恵器系陶器、灰釉系陶器、瓦器、土師器などさまざまであるが、口径はほぼ15~16cmの碗形態に統一されている。また、広域流通品として列島規模で流通した甕壺とすり鉢は、多目的な貯蔵具、あるいは万能の調理具として民間に普及した、厨房の規格的な三点セットであった。この三器種は、食膳具と違って硬質の焼き締め陶器でなければ用をたさないものであり、これらに限って燃料の消耗が激しい窖窯で焼造されたのである。
このように、用途に応じてさまざまの器形と法量に分化していた古代の土器・陶器が、中世には器種・法量とも単純化され、さらに地元製品と中国陶磁器を含めた広域流通品が、都市と農村で独自の複合形態をとり使用されるようになったところに、組成の特質が求められる。つまり、官衙(かんが)への貢納を前提に生産した土器・陶器から、民需品として売りさばくための商品へと基本的な性格を変えたといってよいであろう。
北東日本海域における中世土器・陶磁器からみた中世の黎明は、11世紀後半代に求められるが、中世的組成として完結するのは、珠洲窯が開窯する12世紀中葉ごろである。それは食膳具にみられる「かわらけ」(非ロクロ製土師器皿)と、陶製「すり鉢」の普及という京都系文物の参入が指標となる。なお、10世紀代まで大量に消費されていた土師器の鍋甕類は、姿を消している。土製煮炊具の欠落は、中世後期に九州産の石鍋と畿内産の土釜が多少持ちこまれているのを除けば、以後中世を通して日本海域の大半を含む東日本の一般的な現象となる。これを土製煮炊具に代わり鉄鍋が普及したと確定するには、中世後期の関東・甲信地方で土製煮炊具が多用されることの評価と、鉄鍋の生産と流通実態の究明が必要である。
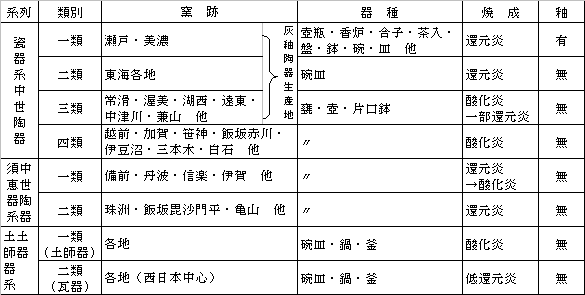
さて、これら中世の焼き物を、楢崎彰一氏の生産技術の系譜による分類にしたがって整理したのが、上の表である(「日本の陶磁」三1975他)。
ここでは、珠洲陶器は須恵器系陶器二類とされているが、貯蔵・調理具を主体に生産した無釉の焼き締め陶器は、瓷器(しき)系と須恵器系に大別される。前者は、平安時代に東海で創成された灰釉陶器の流れをくみ、東海・中部高地から北陸南西部(越前・加賀窯)と近畿周辺に一元的な生産圏を形成した。甕類は須恵器と異質の紐積み・ねじ立て成形により、焚口に分炎柱(ぶんえんちゅう)をそなえた地下式無階単房の窖窯(あながま)で、酸化炎焼成仕上げにより茶褐色に焼き上げる。対して後者は、各地で須恵器の生産技術に改良を加え、多目的な展開をみせている。甕類は須恵器製作の伝統を継承して紐積み・叩き締め成形を行い、須恵器窯を肥大させた半地上式無階単房の窖窯で、還元炎くすべ焼成仕上げにより暗灰色に焼き上げる。戦後まもなく、中世陶器を代表する“六古窯”として喧伝された、瀬戸・常滑・越前・信楽・丹波・備前の各窯は、大体瓷器系によって占められており、戦前以来の陶芸界の価値観を代弁している。
この分類案の大綱は妥当であるが、須恵器系と瓦器、土師器の即物的な区分が至難な事例が少なくないなど、個々の実態はかなり複雑で、多少修正を要する部分がある。たとえば、須恵器系のグループの分類は、瀬戸内の中世窯の調査が進展した現況では、須恵器の伝統をより忠実に踏襲しつつ、甕類の器体を一貫した紐叩打成形とした、東播(とうばん)系諸窯をはじめとする、瀬戸内・四国・九州の諸窯を第一類、叩き締め技法は潜在化しながら、窯構造と焼成技術に固有の展開が認められる備前窯を第二類(丹波以下は瓷器系窯として除外)、器種組成、加飾法に瓷器系の影響が認められる北東日本海域の珠洲系諸窯、および須恵器の製作技術を基調としながら、瓷器系との交渉が一段と顕著な東北太平洋域の須恵器・瓷器折衷系を第三類として包括したい(したがって、飯坂赤川窯は須恵器系に移属)。この他、土師器系も、技術系譜という時間的流れに、地域空間の拡がりを組み合わせると細分が可能視される。 ※参考 〔分類表〕吉岡氏案[その他のファイル/14KB]『中世須恵器の研究』1994より
さらに、こうした生産技術の系譜による分類基準とは別に、生産・流通問題を深化させるため、筆者は、窯構造を含む器質・器種によって規定された分業圏の規模によって、(1)遠隔地窯(2)近国窯(3)地元窯に区分している。現在、中世の焼き物のうち、貯蔵・調理具を主体に生産した、無釉の焼き締め陶器は、大体(1)(2)に属し、その窯跡は50箇所以上にのぼる。こうして、中世陶器窯を全国的に俯瞰しうるようになった現在では、かつての瓷器系=革新的広域型、須恵器系=旧守的狭域型の図式は成立せず、須恵器系が中世陶器で占める比重がきわめて大きかったことが明らかにされ、「中世須恵器」の存在意義が、あらためて問われている。
※画像をクリックすると、拡大図を表示します。