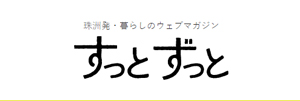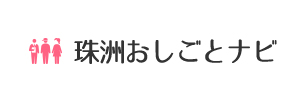本文
国民健康保険で受けられる給付
療養の給付
疾病や負傷などで医療機関等を受診する場合、マイナ保険証を利用または資格確認書を医療機関等の窓口に提示すれば、かかった医療費のうち一部(自己負担割合)を支払うことで次のような医療を受けられます。
- 診察
- 治療
- 薬や注射などの処置
- 入院、看護
- 在宅療養(かかりつけ医による訪問診療)、看護
- 訪問看護(医師の指示による)
入院時食事療養費
入院した時は診療にかかる費用とは別に、下記に示す食事代の一部(標準負担額)を自己負担します。
| 令和6年6月1日から | 令和7年4月1日から | ||
| 住民税課税世帯(下記以外) | 490円 | 510円 | |
|
指定難病患者、小児慢性特定疾病患者(住民税非課税世帯、低所得者1・2を除く。) |
280円 | 300円 | |
|
平成28年4月1日において既に1年を超えて精神病床に入院している患者(住民税非課税世帯、低所得者1・2を除く。) |
260円 | 260円 | |
|
90日までの入院 | 230円 | 240円 |
| 過去12か月で 90日を超える入院 ※1 |
180円 | 190円 | |
| 低所得者1(70歳以上) | 110円 | 110円 | |
※ 住民税非課税世帯と低所得者1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。マイナ保険証を利用する場合、申請は不要です。
※1 90日を超える入院の場合は、改めて申請が必要です。マイナ保険証を利用した場合でも申請が必要です。
療養費
いったん医療費を全額自己負担し、事後に支給申請して必要と認められる場合、療養費として支給されます。下記のいずれも、医師の診断書や意見書、領収書、診療報酬明細書などの書類が必要となります。
- 急病などで資格確認書等を提示せずに医療機関を受診した場合
- 柔道整復師の施術を受けた場合
- 医師が必要と認めた治療用補装具(コルセットやギプスなど)の代金
- 医師の同意を得て、アンマ、はり、きゅうを受けた場合
- 資格喪失後の健康保険で医療機関を受診したため、その保険者に医療費を返還した場合
- 海外で治療を受けた場合(治療目的の渡航は除く)
高額療養費
1か月(月の初日から末日まで)の医療費が自己負担限度額を超えた場合、申請することによって高額療養費が支給されます。
70歳未満の人の自己負担限度額
| 所得※2区分 | 3回目まで | 4回目以降※3 | |
|---|---|---|---|
| ア | 所得901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
| イ | 所得 600万円超901万円以下 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
| ウ | 所得 210万円超600万円以下 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| エ | 所得210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
57,600円 | 44,400円 |
| オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※2 所得とは「基礎控除後の総所得金額等」です。所得の申告がない場合、所得区分アとみなされます。
※3 過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合。
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額
| 所得区分 | 外来+入院(世帯ごと) |
|---|---|
| 現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(1か月の総医療費-842,000円)×1% (4回目以降は140,100円)※4 |
| 現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(1か月の総医療費-558,000円)×1% (4回目以降は93,000円)※4 |
| 現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(1か月の総医療費-267,000円)×1% (4回目以降は44,400円)※4 |
| 所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) |
|---|---|---|
| 一般 | 18,000円 <年間(8月~翌年7月) 上限 144,000円> |
57,600円 (4回目以降は44,400円)※4 |
| 低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者1 | 15,000円 |
※4 過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合。
高額介護合算療養費
年間(8月~翌年7月)の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額を適用後に、合算して下記の限度額を超えた場合は、その超えた額が支給されます。
70歳未満の人の自己負担限度額
| 所得※5区分 | 限度額 | |
|---|---|---|
| ア | 所得 901万円超 |
212万円 |
| イ | 所得 600万円超901万円以下 |
141万円 |
| ウ | 所得 210万円超600万円以下 |
67万円 |
| エ | 所得210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
60万円 |
| オ | 住民税非課税世帯 | 34万円 |
※5 所得とは「基礎控除後の総所得金額等」です。所得の申告がない場合、所得区分アとみなされます。
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額
| 所得区分 | 限度額 |
|---|---|
| 現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
212万円 |
| 現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
141万円 |
| 現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
67万円 |
| 一般 | 56万円 |
| 低所得者2 | 31万円 |
| 低所得者1 | 19万円※6 |
※6 介護保険の受給者が世帯内に複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。
限度額適用認定証
事前に申請することで、医療機関窓口での自己負担が自己負担限度額までになります。70歳以上75歳未満で現役並み所得者3、一般の方は「限度額適用認定証」は不要です。
マイナ保険証を利用する場合、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請は不要です。
移送費
医師の指示によって、やむを得ず病院へ移送されたときに支給されます。
出産育児一時金
国保被保険者が出産した場合に支給されます。(50万円、産科医療補償制度対象でない場合48万8千円)
葬祭費
国保被保険者が亡くなられた際に、葬祭を執行した方に葬祭費が支給されます。(定額 5万円)
訪問看護療養費
費用の一部を支払うことで、訪問看護ステーションなどを利用することができます。
特定疾病療養受療証
高度な治療を長期間継続して行う必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病(慢性腎不全、血友病など)の人は、特定疾病療養受療証(申請により交付)を医療機関等の窓口に提示すれば、自己負担は1か月1万円(人工透析が必要な70歳未満で所得区分ア・イの方は2万円)までとなります。
マイナ保険証を利用する場合でも、特定疾病療養受療証の交付申請は必要です。










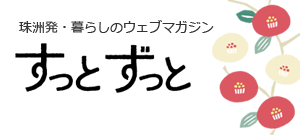
 珠洲市役所
珠洲市役所