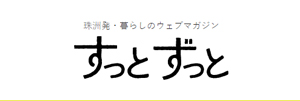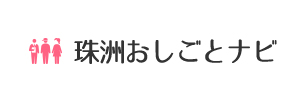本文
介護保険サービス
介護保険で利用できるサービス
介護保険で利用できるサービスは、大きく分けて在宅で受けるサービスと施設に入所して受けるサービスの2種類があります。
「要介護」の認定を受けた方は2種類のサービスのどちらも利用できますが、「要支援」の認定を受けた方は施設サービスを利用することはできません。
在宅でのサービス
| 区分 | 要支援の方(予防給付) | 要介護の方(介護給付) |
|---|---|---|
| 訪問介護 (ホームヘルプサービス) |
利用者が自立した生活ができるよう、ホームヘルパーによる入浴や食事など生活の支援が受けられます。 | ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事や掃除、洗濯、買い物などの身体介護や生活援助をします。 |
| 訪問入浴介護 | 疾病その他のやむを得ない理由により入浴の介護が必要な場合に、入浴サービスを受けられます。 | 介護職員と看護職員が移動入浴車で居宅を訪問し入浴介護をします。 |
| 訪問看護 | 看護師などが訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助をします。 | 疾患などを抱えている人について、看護師などが居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助をします。 |
| 訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士に訪問してもらい、リハビリをします。 | 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、リハビリをします。 |
| 通所介護 (デイサービス) |
デイサービスセンターで、食事・入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、目標に合わせた選択的サービスが利用できます。 | デイサービスセンターで食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りでします。 |
| 通所リハビリテーション (デイケア) |
介護老人保健施設などで、食事・入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーション、目標に合わせた選択的サービスが利用できます。 | 介護老人保健施設や医療機関などで、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りでします。 |
| 居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導をします。 | 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。 |
| 短期入所サービス (ショートステイ) |
介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常生活上の支援(食事、入浴、排せつなど)や機能訓練などが受けられます。 | 介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴などの介護や機能訓練などが受けられます。 |
| 福祉用具貸与 | 歩行器や歩行補助杖などの貸し出しを行います。 | 車椅子、特殊ベット、体位変換器、移動用リフトなどの貸し出しを行います。 |
| 特定福祉用具販売 | 腰掛け便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽などの対象となる用具購入費の9割が支給されます。(年間支給限度額10万円) 申請書はこちらをクリック |
|
| 住宅改修費 | 手すり取り付けや段差解消などの対象となる改修工事費の9割が支給されます。(利用限度額20万円)※住宅改修着工前に「事前申請」が必要です。 ※事前申請から支給決定までの流れ[PDFファイル/51KB] ※支給限度基準額と対象となる工事について[PDFファイル/34KB] 申請書はこちらをクリック |
|
| 地域密着型サービス(住み慣れた地域で生活しながら利用できる新たなサービス) |
|
|
施設でのサービス
| 区分 | 要介護の方(介護給付) |
|---|---|
| 介護老人福祉施設(特別守る老人ホーム) | 寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所します。食事、入浴、排せつなどの日常生活介護や療養上の世話が受けられます。 |
| 介護老人保健施設(老人保健施設) | 病状が安定している人に対し、医学的管理のもとで看護、介護、リハビリテーションを行う施設です。医療上のケアやリハビリテーション、日常的介護を一体的に提供し、家庭への復帰を支援します。 |
| 介護療養型医療施設(療養病床等) | 急性期の治療は終わったものの、医学的管理のもとで長期療養が必要な人のための医療施設です。医療、看護、介護、リハビリテーションなどが受けられます。 |
高額介護(予防)サービス費
介護(予防)サービス費用の利用料の負担が高くなりすぎないように、所得に応じて利用料の自己負担の上限額が設定されます。同じ月に利用したサービスの自己負担額(居住費(滞在費)・食費負担を除く。)が次の額を超えた場合、申請により超えた額が払い戻されます。
| 利用者負担段階区分 | 利用者負担上限額 |
|---|---|
| (1)生活保護を受給されている方 | 個人:15,000円 |
| (2)世帯全員が市民税非課税の方((1),(2)に該当しない方) | 世帯:24,600円 |
| (1)老齢福祉年金を受給されている方 | 個人:15,000円 |
| (2)合計所得額+課税年金収入額が80万円以下の方 | 個人:15,000円 |
| (3)一般世帯(市民税課税世帯で下記(4)以外の方) | 世帯:44,400円 |
| (4)現役並み所得の方※1、2 | 世帯:44,400円 |
※1 現役並み所得:課税所得145万円以上で年収が単身世帯383万円、2人以上の世帯520万円以上の方
※2 令和3年8月から現役並み所得の方の区分が細分化され、上限額が一部変わります。
申請できる人
上記に該当し、自己負担額が上限額を超えた方。(支給対象者には申請書を郵送します。)
申請方法
下記の受付窓口に高額介護サービス費支給申請書を提出してください。
一度申請していただければ、以後は自動的に登録された口座に振り込みます。
注意事項
支給を受ける権利は2年で時効となりますので、お早めにお手続きください。
※高額介護(予防)サービス費支給申請書はこちらからダウンロードできます。
施設サービスを利用した場合の利用者負担
施設入所や短期入所を利用した場合、利用料のほかに、居住費・食費・日常生活費の全額が利用者負担となります。
低所得の人の施設利用が困難とならないように、世帯全員が市民税非課税などの場合には、申請により居住費・食費の負担額が軽減されます。また、利用者負担段階の判定には、利用者の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計額に基づいて決定されています。
※(1)市民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が市民税課税の場合、(2)市民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも預貯金等が一定額(単身1,000万円、夫婦2,000万円)を超える場合のいずれかに該当する場合は対象となりません。
※負担限度額認定申請書はこちらからダウンロードできます。
注意事項
負担限度額認定は、申請された月の初日から有効となります。
有効期限は、毎年7月末日となります。
8月からも引き続き認定が必要な方は、更新の手続きを毎年7月1日から8月31日までの間にお済ませください。
※境界層措置について
介護保険制度においては、次の(1)から(5)に関し、本来適用される基準等を適用すれば生活保護を必要とするが、より負担の低い基準等を適用すれば生活保護を必要としない状態であると福祉事務所長が認めた方については、より低い基準等を適用することとしています。
なお、次の(1)から(5)の境界層措置は、(1)から(5)の順に優先して適用する。
境界層措置が適用される基準
- 給付額減額等の記載
(例)給付額減額等の記載を受けないこととする。 - 居住費または滞在費の負担限度額
(例)介護保険施設の入所にかかる多床室の居住費について、1日につき370円(第2段階)から0円(第1段階)に変更する。 - 食費の負担限度額
(例)介護保険施設の入所にかかる食費について、1日につき390円(第2段階)から300円(第1段階)に変更する。 - 高額介護サービス費にかかる負担の上限額
(例)1ヶ月あたりの利用者負担について、1ヶ月につき、24,600円から15,000円に変更する。 - 介護保険料の金額
(例)介護保険料について、保護を必要としなくなるまでの割合に減額賦課する。
対象者(境界層措置の適用条件)
生活保護の申請者または現に生活保護を受けている方のうち、境界層措置を受ければ生活保護を必要としない方であると福祉事務所長が認めた方(境界層該当証明書の発行を受けた方)。
手続き
境界層措置該当証明書を福祉課に提出してください。










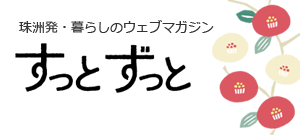
 珠洲市役所
珠洲市役所