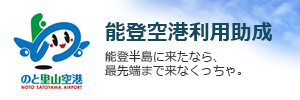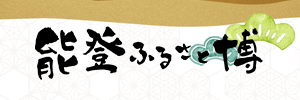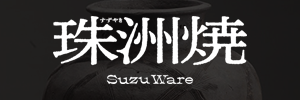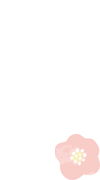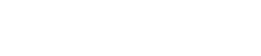本文
文化【伝統】
工芸
珠洲焼


珠洲焼は12世紀後半(平安時代末)から15世紀末(室町時代後期)にかけて中世日本を代表する陶磁器として栄えました。北前船で北海道南部から福井県かけての日本海側に広く流通していましたが、15世紀後半の戦国の世になると忽然と姿を消したことで「幻の古陶」と言われています。昭和53年度に復興してから窯元や陶芸家も増え、独自の技術は昔と変わらず受け継がれています。珠洲焼は鉄分を多く含む珠洲の土を用い、釉薬を掛けずに1,200℃を超える穴窯で数日間焼き締めることで、薪の灰が熔けて自然釉となり黒灰色の落ち着いた美しさを醸し出します。
珪藻土(けいそうど)


珪藻土とは、水中で繁殖する藻類の一種である植物性プランクトン珪藻の遺骸が海や湖の底に沈み、堆積して出来た一種の化石(けい殻)です。珠洲の珪藻土は、土質が良いため切り出したものをそのまま削ってコンロや七輪に仕上げることができます。珠洲は日本で唯一の切り出しコンロの生産地であり、埋蔵量も日本一を誇ります。耐火・断熱性能が抜群で他の素材と比べコンロの外側が火傷するほど熱くなりません。
芸能
砂取節

砂取節は、珠洲市の旧西海村の海岸一帯で歌われていた揚げ浜式製塩の労作歌です。砂取節が伝承されている馬緤地区では、砂取り節祭りが行われています。哀調を帯びた唄に合わせてかすり着に編み笠を被った婦人たちや観光客らで踊りの輪が広がり、夜遅くまでにぎわいを見せます。
ちょんがり節

ちょんがり節 ちょんがり節は、能登一円に伝わる踊り唄で、幕末の頃、願人坊主たちが諸国に持ち歩いたチョンガレ(江戸時代の大道芸・門付け芸でうわれる歌)が派生したものといわれています。語源は「オチョクル」からきたとされており、次から次へと変わった文句(歌詞)を聞かせるのが特徴です。
キャーラゲ(木遣り歌)

キャーラゲとは、祭りの山車(だし)を曳く時に歌われる木遣り節のことです。飯田燈籠山まつりでは高さ16mの燈籠山をはじめ総漆塗の8基の山車を深夜まで曳き廻します。鵜島、上戸の秋祭りでは人形を飾った曳山の上で子どもたちがキャーラゲを披露します。キャーラゲの音頭は各地域で異なり、独自のキャーラゲが響き渡ります。
製法
揚げ浜塩田

珠洲市の外浦地域では約500年前から伝わる揚げ浜式製塩法が今もなお受け継がれています。この製法は、まず海から桶で汲み上げた海水を砂の塩田に弧を描くようにしてまき散らします。海水を含んだ砂を天日で乾燥させると塩の結晶ができます。これを何度も繰り返し、塩分を含んだ砂を箱に集め、再び海水をかけて砂と塩水に分離させます。濃度が高くなった塩水を大釜で煮詰め不純物を取り除くと塩が出来上がります。手間暇かけて作られた天然塩は、添加物など一切使わず自然海水のみで作られているため、体にも優しくミネラル豊富で甘味のある塩です。また、収穫は5月~9月の晴天時に限られるため、大変希少価値が高く生産量が限定されます。
地酒


奥能登には日本酒を造る代表的な杜氏集団、「能登杜氏」があります。江戸時代後期には酒造りをする技能集団として成立していました。当時、冬になると酒屋働きの男たちは「能登衆」と呼ばれ、独自の酒造技術を伝承するために全国各地へ出稼ぎに行きました
伝統の能登流酒造りは全国清酒品評会でも高く評価され、全国的に有名な杜氏の一つとなっています。能登杜氏の里でもある珠洲市には、櫻田酒造と宗玄酒造の蔵元があります。櫻田酒造の銘酒「初桜」や「大慶」は地元漁師町の間で大変人気があり、新鮮な魚介類と晩酌するのには絶品のお酒です。宗玄酒造の代表格である銘酒「宗玄」は、ほのかに甘みがあり濃醇な味わいで、奥能登から全国へと確実に浸透しつつあります。