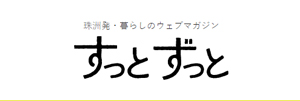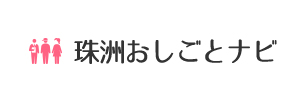本文
珠洲焼館
ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
珠洲焼の展示販売
珠洲焼陶工の力作が勢揃い 54人の珠洲焼を一堂に展示販売
珠洲市蛸島町にある珠洲焼館では、現代の陶工の多彩な作品を展示販売しています。
ゆったりとした広い館内には作品と陶工の写真が展示されており、作り手の思いを感じながら作品を手に取り、ゆっくりと選ぶことができます。
素朴で力強い独特の趣を持つ珠洲焼は、能登のお土産にぴったりです。
皆さんのお越しをお待ちしております。
▼総合サイトにて一部の陶工の作品を販売しております。
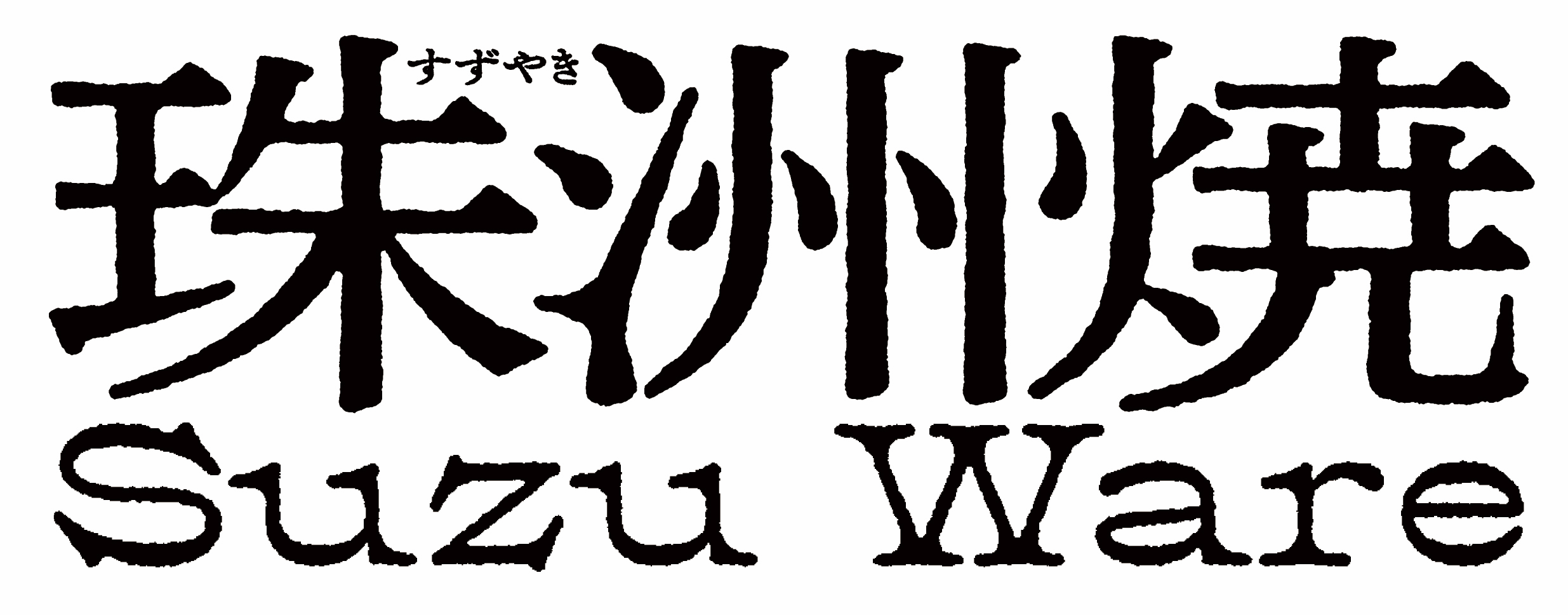 <外部リンク>
<外部リンク>
珠洲焼の歴史
珠洲焼は、12世紀後半(平安時代末)から15世紀末(室町時代後期)にかけて珠洲郡内で生産された、中世日本を代表する焼き物のひとつです。
窯は半島先端部に築かれ、海運により日本海沿岸の東北、北陸の各地や遠く北海道まで運ばれていました。陸上交通が発達していなかった当時において、遠隔地への往来や物資の輸送には、水上交通(海・川・湖)のほうが便利であったと考えられます。焼き物という重量物を出荷する流通コストの面では、日本海に突き出した能登半島は地の利があったといえます。
14世紀には最盛期を迎えて、日本列島の四分の一を商圏とするまでになりましたが、15世紀後半には急速に衰えて間もなく廃絶しました。
窯跡は、宝立町にある法住寺古窯跡をはじめ、約40基の古窯が調査によりわかっています。
珠洲焼の特徴
珠洲焼の特色は、須恵器の系統を継ぎ、粘土紐を巻き上げ、叩きしめて成形を行い、「還元焔燻べ焼き」で焼き上げる点にあります。無釉高温のために、灰が自然釉の役割を果たすことが多く、幽玄ともいえる灰黒色の落ち着いた美しさを醸し出します。
当時は、甕、壺、摺鉢などの日用品が多く焼かれていました。
現代の珠洲焼は当時と作陶工程はほぼ変わらないものの、甕、壺、摺鉢をはじめ、花器、酒器(徳利、ぐい飲み、お猪口)、湯呑、茶器(抹茶碗、急須)、ビアカップ、コーヒーカップ、大皿、小皿、鉢、箸置きなど多様なものが陶工の手によって作られています。
また、その味わいは、使い込むほどに味わいが出てくるものとなっています。
使うことで落ち着いた肌ざわりに
珠洲焼の表面の凸凹は、使いこむことにより角が取れて使いやすくなります。使うほどに落ちついた色つやとなり、自分だけの愛着ある逸品となります。
ビアカップ、ビールジョッキの上手な使い方
釉薬を使わないため、表面の凸凹がビールの泡立ちをきめ細かにしてくれます。最後まで美味しく飲むことが出来ます。あらかじめ、ビアカップやビールジョッキを冷蔵庫に入れ、冷やしてお使いになると、より一層美味しくいただけます。
花器の花が長持ちします
鉄分を多く含んだ粘土で、釉薬を使わず高温で焼き締める焼き方のため、水の浄化機能をしてくれます。水の状態が良く、お花を長く楽しめます。
花器、酒器、湯呑、ビアカップ、コーヒーカップなど多数取りそろえています。
商品の発送いたします。送料はお客様の負担となりますので、ご了承ください。
珠洲焼に関するお問い合わせは、珠洲焼館まで。
電話、Fax、メールなどお気軽にお問い合わせください。
| 珠洲焼館 Suzu Wareshop | |
|---|---|
| 営業時間 | 9時00分~17時00分 |
| 休館日 | 年末年始(12月31日~1月4日) |
| 住所 |
〒927-1204 石川県珠洲市蛸島町1-2-480 |
| Tel | 0768-82-5073 |
| Fax | 0768-82-5074 |
| s-yaki@p1.cnh.ne.jp | |















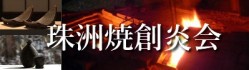
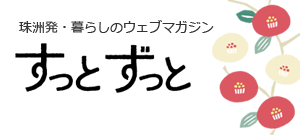
 珠洲市役所
珠洲市役所